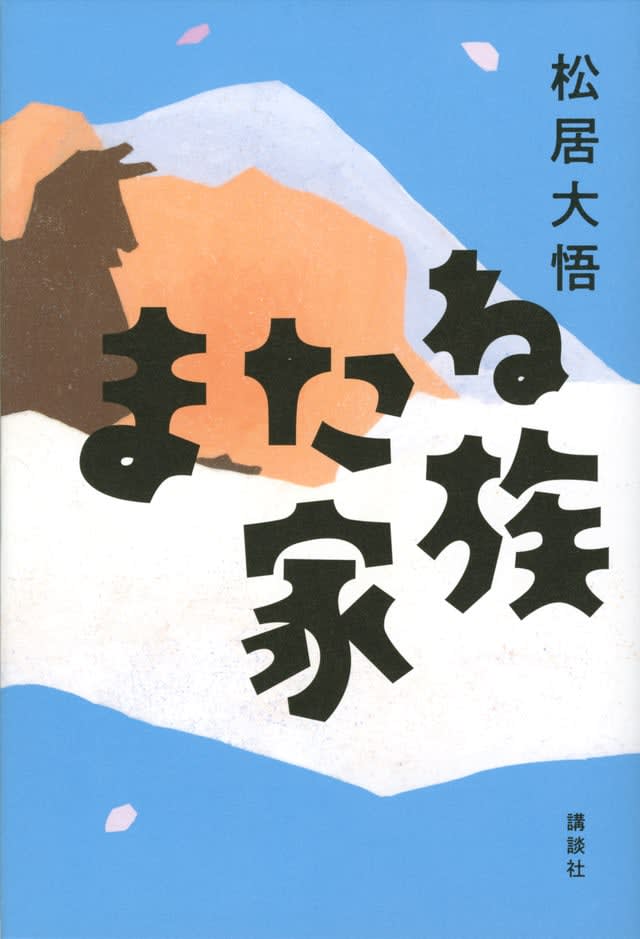
およそ華のある作品ではないだろうと、ページをめくる前から想像できた。だって小さな劇団の作・演出家が主人公の小説だ。
竹田武志は劇団マチノヒの主宰者。物語は彼らの舞台の幕が下りたところから始まる。武志が劇場ロビーで関係者に挨拶をしていると、ポケットの中の携帯が鳴った。
「明日東京で会えませんか」句読点のない父からのショートメール。その直後、兄からの電話で耳にした「……親父、がんだって。肺がん」。それらがきっかけとなり、武志の世界は動きだす。
余命3カ月だという大嫌いな父親。震災を機に噛み合わなくなる劇団。優しかった恋人は女優として知名度を上げ、知らない人のようになっていく。そして、変わりゆく人や環境のなかで、いつまでも過剰な自意識を飼い慣らせないでいる「僕」……。
両親が離婚して以降、十年は疎遠だった父親を見舞うため、武志は東京と故郷である福岡を行き来する。そうしながら彼は自分自身や、家族のありかたについて、少しづつ向き合うようになる。
「父親の死」という決して明るくはない題材だが、軽やかな語り口が印象的だった。限りなく風俗店に近いグレーな学校プレイができるマッサージ店、父方の親戚一同が集まる恒例行事。なんだか珍妙な状況が淡々と描かれていて、思わずふふふと笑ってしまう。
その一方で、武志の周囲の人たちの鋭い言葉に息をのむ瞬間もあるのだ。それらはまっさらなコピー用紙が無防備な指を切りつけるように、残酷なほど鮮やかで、読んでいるだけなのにヒリヒリ痛む。
「あなたは愛情乞食だよ」、「傷つくことから逃げて逃げて、向き合う覚悟がないくせに、たくさんの愛を振りまいて、一人でも多くの人から愛されようと思っている」
「優しい人たちに囲まれて、狭い世界が作れて良かったですね」
「女らしくって何ですか?」
「戦う気がないなら、やるな」……。
言葉を発した彼らは皆、真剣だ。自信のなさを隠れ蓑にして他者と、なにより自分と向き合うことから避けてきた武志を、逃がさないように追い詰める。そして追い詰められ、抜け道も盾も失った武志は、映像を撮りながらついに心で叫ぶ。
「いけ。いけ。もっと、もっとやれ!
一人では何も考えられない。
こうやって作品を作りながら、向き合うことを教えてもらえ。
人と。人と。人を思え。
もっと、もっと。もっと!」――。
予定調和では終わらせないが、伏線は鮮やかに回収する、上質なエンターテイメントとしても楽しめる。けど、そんな表現では片付けられない。弱虫だった若者の真剣勝負が、切実に描かれている。だからなのか、かなりいびつな、個性炸裂の家族の物語なのに、自分の話のようにも思えてくるのだ。
「またね」という別れの挨拶が、希望のような祈りの、祈りのような希望の言葉として、あたたかい光を放っているようなラストシーンだった。その結末は、俯いていた顔を上げて、優しい人たちに別れを告げて、全身全霊で世界と対峙した者にしか辿り着けない場所なのかもしれない。
(講談社 1650円+税)=アリー・マントワネット

