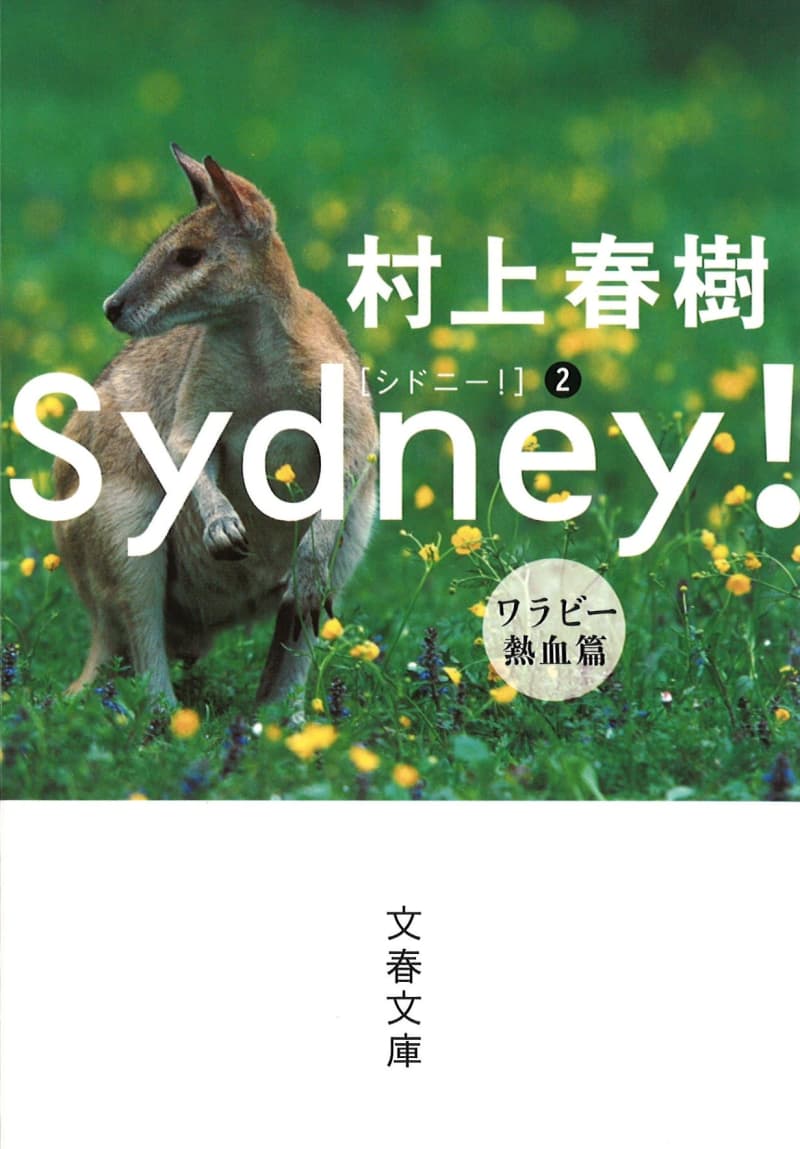
来年の東京オリンピックでのマラソン、競歩を、暑さ対策から、札幌市で開催する方向になったことには、正直驚きました。東京オリンピックなのに、東京都に変更が伝えられたのは国際オリンピック委員会(IOC)の発表前日だったようです。大会組織委員会と小池百合子知事が会場計画見直しなどを巡って対立した相手だったからでしょうか……。
高温多湿のドーハで9~10月に行われた陸上の世界選手権で棄権者が続出。マラソンと競歩は深夜から未明にかけて実施されましたが、それでも女子マラソンや男子50キロ競歩でゴールできた選手は約6割にとどまり、女子マラソンでは68人中40人しか完走しなかったそうです。
早朝にスタートする東京オリンピックでは強い日差しも加わる可能性があるので、以前から議論があった暑さ対策が緊急、最重要な問題となって、急な変更方針となったようです。
確かに、選手に対しても、観客に対して、暑さで倒れてはいけないのですが、それにしても、大会まで300日を切って、突然の変更には驚くばかりです。
コースの選定や、宿泊のためのホテルの部屋があるのか、切符の変更はどうなるか……。変更に伴う費用負担はどうするのか……など、実際的な問題は山積みのようです。
マラソンは大会の花ですし、開催都市の風景の中で行われるので、都市の姿を世界に伝える特別な競技を失う東京としてはたいへん残念でしょうし、2030年の冬季オリンピックの招致を目指す札幌にとっては、都市の姿を世界にアッピールできるチャンスになるかと思います。10月30日からのIOC調整委員会での議論を残してはいるのですが……。
☆
ドタバタした今回のマラソン開催地変更のニュースに接して、村上春樹がシドニー・オリンピックを現地で観て書いた『シドニー!』(2001年)を久しぶりに読み返しました。それは、この本の最後、二人のマラソンランナーに村上春樹がインタビューしていたからです。
『シドニー!』は、これまでこの「村上春樹を読む」では紹介したことがないかと思いますが、村上春樹の価値観や感性の働き方を知るにはいい本かと思いますので、今回は『シドニー!』について書いてみたいと思います。
読み直して、思ったことをまず記してしまうと、村上春樹の「敗者への視点」が迫ってくる本です。最後に村上春樹がインタビューしている二人のマラソン・ランナーは、シドニー・オリンピックの男子マラソンで途中棄権した犬伏孝行と、女子マラソンのバルセロナ・オリンピックで銀メダル、アトランタ・オリンピックで銅メダルをとりながら、シドニー・オリンピックには参加できなかった有森裕子です。
もちろん、村上春樹自身がマラソンのランナーであるから、マラソン選手のことを描いているのでしょうが、例えば、こんな言葉があるのです。
本の冒頭、1996年7月28日に、アトランタ・オリンピック女子マラソンの時の有森裕子の走りながらの思いが描かれているのですが、そこに「ここでもそこでも私は勝ち、同時に負ける」と書かれています。この言葉が静かに私の中に入ってきました。
アトランタ・オリンピックの女子マラソンの最後のひどい坂道を上り、ようやく有森裕子のアトランタの42キロがあと少しで終わろうとしているのですが、「でも一方では、何ひとつ終わりはしない。彼女にはそれがわかっている」と記されています。
続いて「バルセロナのときにはわからなかった。だからその後の何年かのあいだ、ずいぶん苦しむことになった。でも今はわかる。これが終わりではない。何かべつのものの新たな始まりなのだ」とあって、「ここでもそこでも私は勝ち、同時に負ける」と記されているのです。
☆
シドニー・オリンピックは南半球でのオリンピックですので、暑いわけではなく、むしろ寒さも感じる気候のようです。9月13日(水曜日)「マラソン・コースをまわってみる」の日誌には「部屋の中はすごく寒い」とありますし、閉会式の翌日の10月2日(月曜日)の「祭りのあと」では「朝はずいぶん冷え込んで、僕はセーターの上にウィンドブレーカーを着込ん」だことが書かれています。
ですから、暑さ対策から開催地変更されるという今回の東京オリンピックのマラソン・コース問題とは、まったく異なるのですが、男子マラソンの犬伏孝行は脱水症状を起こして、「三十キロの前あたりから、身体はまったく動かなくなって」三十八キロ地点で、棄権しています。
座り込んで、担架が来るのを待ち、救急車で競技場の医務室まで運ばれました。「自分で水を飲もうとしても飲めない」状態で、点滴で1リットルほど水分を入れてもらってようやく落ち着いたようです。
でも実はかなり危険な状態だったようです。河野匡監督によると、棄権者を収容する車がくるまで、長いあいだ待っていなくてはなりません。一時は体温が33度まで下がっていました、32度まで下がったら、生命が危ないところだったそうです。点滴を受けて、犬伏選手の体温もようやく35度7分まで上がったそうです。このように、酷暑の環境でない中のマラソンでも、過酷な競技であることは間違いないのです。
☆
シドニー・オリンピックの女子マラソンで、優勝したのは、高橋尚子です。最後にシモンが追い上げてくる場面を覚えている人もいるでしょう。
9月24日(日曜日)「いよいよ女子マラソン」には、そのシモンについて「この人の身体はいつ見てもきっちりと堅く締まっている。猫背気味にひょいひょいと身体を揺すって走るが、それで振り子のように全体に勢いをつけている。実をいうと、この人のフォームが僕はわりに好きだ。脚の筋肉の力がよほど強くないとこういう走り方はできない」と、さすがマラソン・ランナーらしい見方を村上春樹はしています。
それに対して「高橋のフォームは対照的だ。身体全体をコンパクトに使って無理なく走る。脚力や筋力の力強さはシモンには劣るけれど、軸をまっすぐに立てて、極力無駄を省き四十二キロを走り抜く。シモンが力の走りなら、高橋はフォーム・コンシャスな走りだ」と加えています。
村上春樹は競技場のメディア席に陣取って、テレビのモニターを見ながら、トップの選手がスタジアムに現れるのを待っているのですが、トップの高橋尚子を、競技場に入る手前からシモンがぐんぐん追い上げてきます。脚もしっかりと伸び、ストライドも大きくなり、「まるで『ターミネーター』みたいだ」と村上春樹は書いています。「彼女はたぶん勝つつもりでいる。僕はこの人のこういう理不尽なしつこさがわりに好きなんだけど」と加えています。
でも、高橋尚子は、トラックの最後の直線に入って後ろをちらりと振り向くが、そのままペースを乱すことなくゴールイン。優勝タイムは2時間23分14秒で、オリンピック新記録でした。ちなみに1956年のメルボルン・オリンピックでの男子マラソンの優勝者のタイムは、この高橋尚子より遅い2時間25分だったそうです。
☆
翌9月25日(月曜日)の高橋尚子の記者会見にも村上春樹は参加しています。
「間近で観る高橋尚子はとても感じのいい女性だった。きっと誰でも彼女に好感を持つことだろう」と書いています。「微笑みを絶やすことなく、聞き取りやすい声で、淀みなく、はきはきと質問に答えてくれる。もし彼女が銀行の窓口に座っていたとしたら、僕だって思わず余分に預金しちゃうかもしれない」と書いていますし、「ただ感じがいいだけではない。彼女は見たところ自信に満ちているし、頭の回転だって速い(もっとも僕は、頭の回転の鈍い一流アスリートにまだ会ったことがないけれど)」とも記しています。
さらに高橋尚子は国民的英雄(ヒロイン)のイメージを既に持っていて、何かが明るく輝き、「そのイメージを身にまとってこれから先の人生を生きていくことになるだろう。二十八歳の女性にとっては、ずいぶん長い道のりだ」とも書いているのですが、でも「あえて正直な感想を言わせていただくなら、僕はこの日の記者会見で、彼女によって語られたものごとに対して、それほど幸福な気持ちを抱くことができなかった。少なくとも高橋尚子の素晴らしい走りを見ているときほどは、幸福な気持ちになれなかった」と記しているのです。
その理由は「できることなら、もっとありありとした、正直なぎざぎざのある話を、彼女自身の言葉で聞きたかった」からのようです。話の枝がいささかきれいに払われすぎていて、話の中身がもうひとつ腹にしみてこなかったようです。
さらに、村上春樹は「自分の印象は正しくないかもしれない」と自省しながらも、「人の話を日常的に職業的に聞いている人間として、そこにはもっと何か立体的なものが潜んでいるはずだという直感を持った」と書いています。
☆
2000年の11月5日、ニューヨークでNYシティー・マラソンが行われた日の翌日、有森裕子に対する村上春樹のインタビューが行われています。その時、日本は高橋尚子のシドニーでの金メダルに、まだ沸いていました。彼女は国民栄誉賞を獲得し、あらゆる雑誌の表紙を飾り、日本シリーズの第一戦で始球式のボールを投げたりしていました。小出義雄監督の著書『君ならできる』は日本全国の書店で、ベストセラーリストのトップを飾っていたという時期です。
このインタビューで、最も印象的なものは、有森裕子が自分の弱さを抱えて生きている姿を語っていることです。
☆
例えば、専属のコーチを持たない有森裕子は、自分の練習の日程を書いたノートをいつも大事に携えています。左側に日々の達成するべき目標が書き付けてあり、右側には実際に行なった練習が書き付けてあるのです。「それが、ロールシャッハ・テストの図形みたいに、左右対称にぴたりと合致することが理想だ。しかし場合によっては、彼女が理想に合わせる前に、理想の方が歩み寄ることもある」と村上春樹は書いています。
ようするにこういうことです。「いつもは左側の目標をボールペンで書くんです。でも今年は鉛筆で書きました。いつでも消せるように。つまり体調があまりよくなかったりすると、消しゴムで左側の数字をごしごしと消して、べつの数字を書き込むようになったわけです。そういうところが、一人でやっていると甘くなってしまう点かもしれません」と有森裕子は語っています。
そして「指導者がいないことのいちばんつらい点は、自信をなくすことです」と彼女は静かな声で話しています。「自分が今どこにいるのか、それが正しい場所なのか、そうではないのか、判断をいつも自分で下さなくてはならないということです」
ときとして、彼女は途方に暮れる。そう村上春樹は書いています。
☆
こんな話をしているのは、前日のNYシティー・マラソンで(村上春樹も三度めの同マラソンを走っていますが)有森裕子は10位で、2時間31分という不本意な時間でした。有森裕子にとってのレースは二十三キロの地点で終わっていて、あとの二十キロほどは、もう見込みのない身体を、「かたちをつけたタイム」でなんとかゴールまで運ぶことだけでした。労多くして報いの少ない作業です。
☆
「どうして有森裕子はNYシティー・マラソンで勝てなかったのか? 僕の目から見れば、あるいは彼女自身の目から見ても、理由はかなり明らかだった。ひとことで言えば、走り込みの不足だ。夏場の長い距離の走り込みが思うようにできなかった。だからあとでどれだけスピード練習を積み重ねていっても、体調を万全に整えても、長丁場を高速で乗り切ることはできなかった」と村上春樹は指摘しています。
「フルマラソンのためのトレーニングの原則はほとんどの局面において、エリート・ランナーでも、(僕みたいな)市民ランナーでも基本的にはだいたい同じである。目標を設定した段階から、なるべく長い距離を走る練習を積んでおく。レースの二カ月前くらいからはスピードをつける練習をする。二、三週間前からは練習量を落として最後の調整にかかる。長い距離を走る時期には少しでも長い距離を走った方がいいし、スピード練習のスピードはなるべく速い方がいい。それだけ。原理としては、簡単なことなのだ。しかし実際に実行するのは、決して簡単なことではない」と、マラソン・ランナーらしい具体的な解説を村上春樹がしています。
「そして有森裕子は、残念ながらその『長い走り込み』の部分を思うように積み上げることができなかった。どうしてか? 答えはひとつ。集中力が欠けていたからだ――というのが僕の受けた印象だった」
☆
理想的練習目標に対して「彼女が理想に合わせる前に、理想の方が歩み寄ることもある」ことを、有森裕子が語っているのは、こんなNYシティー・マラソンの結果の後のインタビューであったからもあるのでしょう。
有森裕子は9月にシドニーに行って、女子マラソンのテレビ中継の解説の仕事をしています。「そのシドニーに行くという話を、六月にボールダーで本人の口から耳にしたとき、正直なところ首を傾げないわけにはいかなかった。彼女は現役のランナーだし、シドニー・オリンピックは何があっても出たいと願っていた大会だった。そんなところに顔を出すよりは、ボールダーに腰を落ち着けて世間の雑音を避け、NYシティー・マラソンに向けてじっくりと練習に励んでいた方がいいのではないのかと思った」と書いています。
このあたりが集中力を欠いて「長い走り込み」の部分を思うように積み上げることができなかった理由ではと、村上春樹が考えているのかもしれません。
☆
現地シドニーで、高橋尚子の金メダルを見ながら解説していたのですが、有森裕子は「高橋が金メダルを取るのはわかっていたんです。何か余程のことがないかぎり、彼女が勝つのは確実でした。小出監督と高橋のコミュニケーションはそれくらい完壁だったんです。ほんとに、ただごとではないくらいすごかったです。ここまで一人の人間にのめりこむことができるのかというくらいに。だからまあ、土壇場になって大きな故障でもないかぎり、よもや金メダルを逃すことはないだろうなと、私は考えていました」と語っています。
有森裕子も小出監督の下で練習した選手ですが「私は監督から指示を出されても、納得のいかないことがあると、納得がいくまでしつこく質問しました。それでも納得できないことは、納得がいかないとはっきり口にしました。そんな風に言うと、いつもお前はわがままだからと言われました。素直に言うことを聞かないから、お前は金メダルを取れなかったんだとも言われました。でも、そう言われたときに、私はつくづく思ったんです。金メダルっていったい何だろうって。金メダルを取るために、自分というものをそこまで捨てなくてはならないんだろうか。一人の人間としての自分を、そこまで消さなくてはならないんだろうかって」と村上春樹に語っています。
☆
女子マラソンのランナーが、トップでやっていくためには男とつきあっては駄目だと言われるそうです。恋人がいると、選手はつらいことがあると、そこに逃げてしまうからです。だから監督としては、なんとしても逃げ場を作らせないようにするんだそうです。自分が100パーセント、相手をコントロールできるようにしておきます.その方が効率がいいのだそうです。
だが有森裕子は、そういうマラソン・ランナーに疑問を抱いていたようです。
「でもそれは本当に正しいことでしょうか? だってそういう勢いだけでやっていける年齢というのは、人生の中で本当に限られていますよね。だからその年齢を過ぎてしまうと、あとはろくに走れないということになってしまいます。それが今の日本のマラソン・ランナーの現実です。それが正しいことだとは、私には思えないんです。そうじゃなくて、結婚をしたり、家庭を作ったりというなかで、人生を通して、自然なかたちで長く競技とつきあっていくということが、本当は大事なんじゃないでしょうか。私が言いたかったのはそういうことなんです。そして私がなりたいと思っているのは、そういうランナーなんです。
でもそんなことはどうでもいいんでしょうね。私はランナーがまず人間としてどうこうなんて言っていますが、見当違いなのかもしれません。ランナーに人間的なものを求める人なんて、とくにいないのかもしれません(笑)。オリンピックで金メダルを取ること、おそらくはそれがいちばん重要なことなんでしょう。
ご存じのように、この世界では勝てば正義なんです。そして私はそのことをあれこれ言っているわけではありません。私だってその正義にある程度のっかってきた人間ですから、偉そうにひとのことは言えません。でもそれはそれとして、私は私が求めているランナーの姿に自分を少しずつ近づけていきたいと思っているんです」
☆
長々紹介してきましたが、有森裕子の話は、自分の弱さも語り、自分の信念も語り、さらに望まない仕事でもプロとして生きていくために引き受けなくていけないことも語り……という、村上春樹の言う「ありありとした、正直なぎざぎざのある話」になっています。
☆
この「シドニー!」の最後に、なぜ、犬伏孝行と有森裕子の2人を登場させたかについて、村上春樹は「彼らは優れた才能を持つアスリートであり、高い場所を志し、歯を食いしばって厳しい練習を耐えてきた。それぞれの生き方を持ち、夢と野心を持っていた。そしてそれぞれの弱みを抱えていた。つまり、そう、僕やあなたのように」と記した後、次のように書いています。
以下の文章もたいへん長いですが、この本の結末の最も大切な部分かと思いますので、紹介してみましょう。
「僕らはみんな――ほとんどみんなということだけれど――自分の弱さを抱えて生きている。僕らは多くの場合、その弱さを消し去ることも、潰すこともできない。その弱さは僕らの組成の一部として機能しているからだ。もちろんどこか人目につかない場所にこっそりと押し隠すことはできるが、長い目で見ればそんなことをしても何の役にも立ちはしない。僕らにできるもっとも正しいことは、弱さが自分の中にあることを進んで認め、正面から向き合い、それをうまく自分の側に引き入れることだけだ。弱さに足をひっぱられることなく、逆に踏み台に組み立てなおして、自分をより高い場所へと持ち上げていくことだけだ。そうすることによって僕らは結果的に人間としての深みを得ることができる。小説家にとっても、アスリートにとっても、あるいはあなたにとっても、原理的には同じことだ」
さらに、こうも述べています。
「もちろん僕は勝利を愛する。勝利を評価する。それは文句なく心地よいものだ。でもそれ以上に、深みというものを愛し、評価する。あるときには人は勝つ。あるときには人は負ける。でもそのあとにも、人は延々と生き続けなくてはならないのだ」
☆
有森裕子はバルセロナ・オリンピックで銀メダル、アトランタ・オリンピックで銅メダルで、このような二大会連続のオリンピック・メダル獲得は、日本女子陸上選手では有森裕子が初です。でもオリンピックの女子マラソンの金メダルという点だけから見たら、敗者であるということなのでしょう。
その有森裕子の話は読む者によく伝わっています。「理想に合わせる前に、理想の方が歩み寄ることもある」有森裕子の弱さに(アスリートはそうであってはいけないのでしょうが、でも)親しみを感じてしまいます。
オリンピックという巨大な装置の場で、頂点にたった巨人たちの世界を描くのではなく、そのアスリートたちの弱さや孤独を描いたところに、この村上春樹『シドニー!』というオリンピック観戦記の特徴と意味があると思います。
☆
1点、2点だけ追加しておきます。
シドニー・オリンピックは、オーストラリア先住民アボリジニのキャシー・フリーマンが女子400メートルで金メダルを獲得したことで記憶に残る大会でもあります。フリーマンは開会式では聖火をともしていて、同じ一大会で聖火をともし、金メダルを獲得したのはフリーマンだけだそうです。
優勝して金メダルを決めたのに彼女は「ほんの少しだけ小さく手をあげる」だけでした。そして観客席のいちばん前にいた家族と手を取り合い、抱擁すると、やっと自分というものが戻ってきて、表情がゆるみ、穏やかな笑みが湧き水のようにしみ出してきて、両手を挙げて、何かを叫びました。彼女は深く悩み、傷つき、迷いさまよっていたのです。
「このシーンを見るためだけでも、今夜ここに来た価値はあったと思う。胸が熱くなった。人の心の中で、固くこわばっていた何かが溶けていくのがどういうことなのか、それをまぢかに目撃することができた。今回のオリンピックの中でも、もっとも美しく、もっともチャーミングな瞬間だった」と村上春樹は書き記しています。
別なところでも「キャシー・フリーマンの四百メートルの優勝シーン。これがどれくらい圧倒的で、どれくらいマジカルなものであったかは、その場に居合わせない人には、本当には理解できないだろうと僕は信じています。それくらい素晴らしい出来事だった」と村上春樹は記しています。そのことの意味をより深く知るために「オーストラリアの歴史の村上簡略版」というわかりやすい文章もあります。キャシー・フリーマンについてのところを読むこともお勧めです。
さらに「高橋尚子がゴールの競技場に姿を現したときに僕が感じた気持ちも、言葉ではちょっと言い表せない種類のものです。そのときの競技場の空気の揺れのようなものは、たぶんテレビの画面からは伝わらないはずです。僕はそこにあった空気の匂いや、光線のあたり方や、人々のどよめきを、ずっと長く覚えていることになるだろうと思います。それはなんというか、特別なものでした」と村上春樹は書いています。(共同通信編集委員 小山鉄郎)
******************************************************************************
「村上春樹を読む」が『村上春樹クロニクル』と名前を変えて、春陽堂書店から刊行されます。詳しくはこちらから↓

