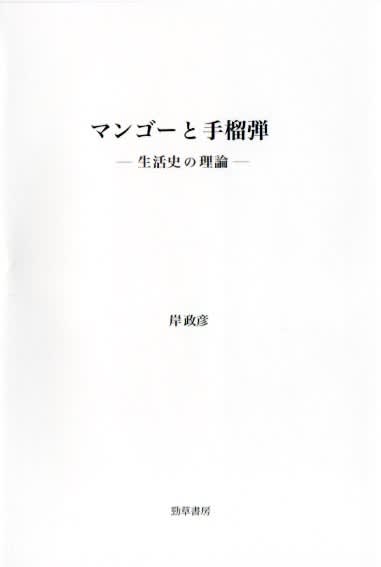
切れば血の出る理論書とでも言おうか。沖縄や被差別部落のフィールドワークを続けてきた社会学者が、個人の生活史の聞き取りをめぐる課題と可能性を論じた。全編に調査対象者の語りが引用され、本書に異様な迫力を与えている。
冒頭、沖縄戦の集団自決を体験した80歳の女性の語りに慄然とする。日本兵から渡された手榴弾で周りが次々に爆死する中、自分の家族が手にした手榴弾は不発弾だった。父に手を引かれ逃げる途中、父は米軍の迫撃砲に倒れる。背中にかぶった土や石が実は父親の骨であり血だったと背後で目撃した弟から告げられたのは、戦後50年経ってからだった。
こうした個人の語りを事実から切り離し、語り手と聞き手の間に構築されたストーリーとして相対化する「構築主義」の立場を著者は取らない。たとえ間違いや誇張を含んでいても、それは歴史と社会構造に結びついたまぎれもない事実である。誤りは訂正を重ねて真実に近づけばいい、という。
集団自決の現場から逃げ延びたその女性は森の中に5カ月間、数家族と隠れ住む。男たちは暇に飽かせて葉を枯らし、手作りのタバコを吸っていた、と語る。過酷な状況にそぐわないほほえましい挿話から、人はどんな状況にあっても生きる喜びや楽しみを見出すことを私たちは知る。
こうした「人間に関する理論」を豊かにする作業に終わりはない、事例報告を無限に繰り返すだけだ、と著者はいう。現場に根ざす研究者の自負と情熱が静かに伝わる。
(勁草書房 2500円+税)=片岡義博

