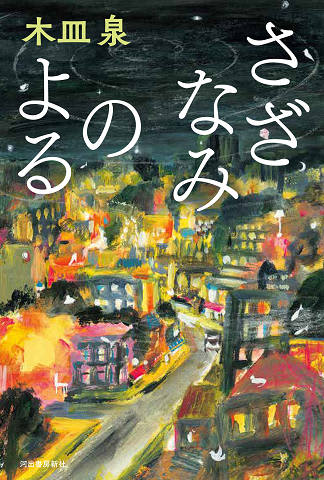
物語は、病気で死にかけている女・ナスミの述懐から始まる。弁当を食べ終わった夫が、その弁当箱を折りたたむ姿を思い返し、ナスミは実感する。いろんな場面でプリプリと怒りながら生きてきたけど、今は「ありがとう」しか浮かばない。私は、私が思っていたより、すでに百倍、幸せだったのだと。
『すいか』『野ブタ。をプロデュース』『昨夜のカレー、明日のパン』など、観るものの涙腺をジワッとさせる脚本家・木皿泉の小説最新作。登場人物は、2016年と2017年の年始にNHKで放送されたドラマ『富士ファミリー』と重なる。
ドラマでは、遺された家族と、その家族が営む何でも屋「富士ファミリー」に巻き起こる人情喜劇が描かれたが、小説版はナスミの死について、姉の鷹子や妹の月美、夫の日出男ら、周辺の人々の内面が丁寧に描かれる。小説の強みとはこれである。みんなが、ほんとうは何を考えていたのか。どうやって、受け入れがたい喪失と、共に歩いて、生きているのか。
ナスミへの思いはさざ波のように、外へ、外へと広がっていく。ナスミの幼馴染。その妻。ボーイフレンドの妹。かつての同僚。彼らの中に、ナスミは、他の人とは違う感触を残している。いつも大切で、いつも大好きで、いつも一緒にいたわけではなかったけれど、ナスミは彼らにとってはっきりと「特別な誰か」である。二度と会えない人。自分を変えてくれた人。ナスミは、読めば読むほど、女性から見ても味わい深くてかっこよく、なんだろう、とても会いたくなる。「会いたい」は「恋しい」に近しい。そう、いつのまにか読者も、「ナスミを思う人を眺める側」から「ナスミを思う側」に立たされているのだ。
語り手が変わるたびに、ナスミの人物像が多面的になっていく。家族の知らないナスミや、同僚の知らないナスミが、ひとつずつ、明らかになる。一貫しているのは、ナスミはいつも誰かのために、怒ったり、隣りに座ったり、言葉をかけたり、していることだ。自分については苦い思いをいっぱいしたから、もう、自分のことばかり考えるのはやめようと。
ナスミはあなたに呼びかける。あなたの欠落を埋めるものは、すでにあなたの手の中にあるのだと。
(河出書房新社 1400円+税)=小川志津子

