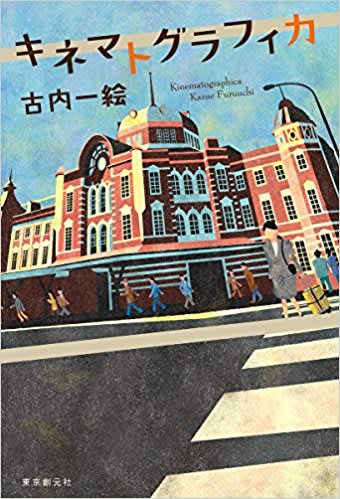
「好きなことを仕事にできるって、いいねえ」。幼い頃、作文が得意だった私に、今もあまたの旧友たちが、何の悪意もなく、むしろ善意で、かけてくれる言葉である。
本作は、平成元年に大手映画会社に入社した、同期の桜たちの回顧の物語だ。映画の知識は誰にも負けないのに、それが何も生かされない営業職に鬱々とする者。「結婚」にまつわる恋人からの無言のプレッシャーに辟易する者。映画にはそんなに思い入れはないけれど、多少の困難ならそれなりにしのげる(と本人は思っている)者。それぞれに誇りがあり、それぞれに悩みがある6人の仲間たちが、とある古い日本映画の貸出スケジュール管理をしくじり、群馬から大阪、そして名古屋、さらに福岡へと、35ミリフィルムの巨大な巻き物を、わっせわっせとリレーする。物語は、それぞれの持ち場でのエピソードと、彼ら自身の人生の回顧とを連ねるようにして進む。
胸に刺さるのは、「初めての女性営業職」としてもてはやされる、北野咲子のエピソードだ。彼女は自分の役割を、わかりすぎるぐらいにわかっている。「営業職を任されるほどの優秀な女性」として扱われれば扱われるほど、「自分はそれ以上に優秀でなければいけない」と思っている。幼い頃から、病弱な妹のために、人に甘えることを自分に禁じて育った彼女は、多少の理不尽に対して「怒る」というスイッチをそもそも備えていない。
そんな彼女と連帯を見せるのが、これまた異例の「国際部」に配属された小笠原麗羅である。自分の女性上司が咲子にひどい仕打ちをした、その仕返しを彼女は周到にやってのける。麗羅は咲子に、姉の姿を見ている。裕福な自分の育ちを嫌悪して、自分に幸せを禁じるみたいにして、遠い異国へと去った姉のことを。
彼女たちにとって、それ以降の日々は闘いの歴史である。自分たちの志を遂げるまでは、心休まる素朴な優しさや温もりになど心を揺らさないと決めている。誰かにとっての「加害者」になることだっていとわない。
そして、26年後。50代になった彼女たちを、さらなる境地が待ち受けていた。
「好きなことを仕事に」し続けてきたからこそ、感じる痛み。虚しさ。ここで描かれるのは、それである。職業人であることを理解してくれていたはずの家族でさえ、いざとなったら「母親であること」を礼賛する。これは何だ。今までの踏ん張りは何だったのだ。咲子の肩は虚しさに震え、麗羅は黙って彼女の手を握る。
そんな彼女たちを救うのは、次世代の理解者の登場である。自分の目で見て、耳で聞いたことだけが「世界」ではない。「理解」というエールは、時を越えて、本当に必要なときに目の前に現れる。何歳になっても、先など見えないけれど、でもいつだって救いはそんなふうにして、いきなり自分を捕まえて抱きしめる。だから、大丈夫。どんなにひっくり返ったって、人は、ひとりでなどありえないのだ。
(東京創元社 1600円+税)=小川志津子

