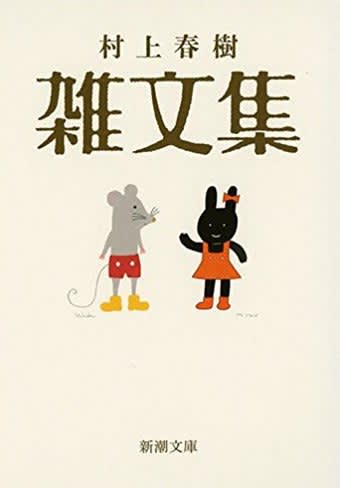
「寒い冬の夕暮れに僕はなじみのレストランに入って、ビール(サッポロ中瓶)と牡蠣フライを注文する。この店には五個の牡蠣フライと八個の牡蠣フライというふたつの選択肢がある。とても親切だ。たくさん牡蠣フライを食べたい人のためには、たくさんの牡蠣フライが運ばれてくる。少しの牡蠣フライでいいという人のためには、少しの牡蠣フライが運ばれてくる。僕はもちろん八個の牡蠣フライを注文する。僕は今日、たくさんの牡蠣フライを食べたいのだから」
村上春樹の「牡蠣フライの話」は、そう書き出されています。こんな村上春樹の小説は読んだことがないという人がいるかもしれません。
それは、この「牡蠣フライの話」が『村上春樹 雑文集』(2011年)の中に収録された「自己とは何か(あるいはおいしい牡蠣フライの食べ方)」というエッセイの末尾に、「牡蠣フライ」を通して「自己とは何か」「自分とは何か」を思考する実践編として置かれた小説だからです。
☆
前回の「村上春樹を読む」で、食べ物のことがしばしば登場する村上春樹作品の中でも屈指の食の名場面である『ノルウェイの森』(1987年)の「キウリの海苔巻き」のことを紹介しました。これは脳腫瘍で入院している「緑」の父親を「僕」と「緑」が見舞いに行って、食欲のない「緑」の父親に「キウリの海苔巻き」という美味しい食べ物を食べさせてあげる話です。興味がありましたら、先月のこのコラムを読んでください。
せっかく、村上春樹作品の食べ物のことについて書いたので、今回は村上春樹が食べ物のことを例にあげて、自分が考える文学の形について語っていることを2つほど紹介してみたいと思います。
その1つが、「牡蠣フライ」です。村上春樹の牡蠣フライ好きは有名です。紹介した「自己とは何か(あるいはおいしい牡蠣フライの食べ方)」という文章の中にも、もちろん「牡蠣フライが好きなので」と村上春樹は記しています。
他にも、読者とのインターネットを通した応答集『村上さんのところ』(2015年)の中にも何回か、牡蠣フライに触れたところがありました。
「よく牡蠣食う客」という36歳の女性からの「カキ小屋に是非いらしてください」というメールには、1人で2、3キロの牡蠣を食べてしまった後、「お店のおばちゃんがささっと残りをカキフライにしてくれて、それがまぁビックリするくらい美味しくて。未だにあのカキフライを超えるものに出会ったことがありません」などと書いてありますが、このメールに対して、村上春樹は「読んでいるだけで口の中につばがたまりそうです。すごくおいしそうですね」「僕は牡蠣ってほんとにほんとに好きなんです」と、牡蠣フライばかりでなく、自分の牡蠣好きを述べています。
☆
また東日本大震災(2011年3月11日)後に福島県郡山市で始められた文学講座「ただようまなびや 文学の学校2015」(2015年11月29日)に村上春樹が参加。その場でも「僕はカキフライが大好きです」と話しているようです。
新聞の報道などによると「でも、うちで食べることってまずないんです。うちの奥さんが揚げ物が一切イヤなので、出してくれないんです。結婚して45年になりますが、結婚したあとで、揚げ物が苦手だということが判明した」とか。
仕方なく、村上春樹は牡蠣フライが食べたい時は、奥さんが出かけた時などに、自分で作るそうです。それを「1人カキフライ」と村上春樹は名づけています。その「カキフライは揚げたてを食べるのはおいしいです。でも、寂しいです。おいしいけど寂しい、寂しいけどおいしいという、永遠に循環していくわけです」と、1人カキフライについて語っています。
そして、小説を書くことも、同じように孤独な作業で、「1人カキフライ」にすごくよく似ていることを話したようです。
ですから、小説を書いている時は、小説を書いているんだとは思わないようにしていて、それよりは「いま僕は、台所でカキフライを揚げているんだ」と考えるようにしているそうです。
「皆さんも、もし小説をお書きになるようなことがあれば、カキフライのことを思い出してください。そうすると、すらすら書けます」とも述べたようです。
☆
さて、これら村上春樹の牡蠣フライに関する言及の意味することは何でしょうか。
それを考える原点のような文章が、冒頭に紹介した「自己とは何か(あるいはおいしい牡蠣フライの食べ方)」なのです。
この一文は村上春樹の文学・物語について、深く語っていて、実に興味深いです。
その中で、「『自分とは何か?』という問いかけは、小説家にとっては―というか少なくとも僕にとっては―ほとんど意味を持たない。それは小説家にとってあまりにも自明な問いかけだからだ。我々はその『自分とは何か?』という問いかけを、別の総合的なかたちに(つまり物語のかたちに)置き換えていくことを日常の仕事にしている」と村上春樹は述べています。
さらに、しばらく前にインターネットで、読者から「先日就職試験を受けたのですが、そこで『原稿用紙四枚以内で自分自身について説明しなさい』という問題が出ましたが、僕はとても原稿用紙四枚で自分自身を説明することなんてできませんでした」というメールが届き、「もしそんな問題を出されたら、村上さんはどうしますか? プロの作家にはそういうこともできるのでしょうか?」と質問されたようです。
☆
それに対する村上春樹の答えは次のようなものでした。
「原稿用紙四枚以内で自分自身について説明しなさい」ということは、意味のない設問のように思える。でも「自分自身について書くのは不可能であっても、たとえば牡蠣フライについて原稿用紙四枚以内で書くことは可能ですよね」と述べて、さらにこんな「牡蠣フライ理論」を展開しています。
つまり「あなたが牡蠣フライについて書くことで、そこにあなたと牡蠣フライとのあいだの相関関係や距離感が、自動的に表現されることになります。すなわち、突き詰めていけば、あなた自身について書くことでもあります。それが僕のいわゆる『牡蠣フライ理論』です」と記しているのです。別に牡蠣フライでなくてはいけないことはなく、メンチカツで海老コロッケでもかまわないそうです。さらにトヨタ・カローラでも青山通りでもレオナルド・ディカプリオでもいいそうです。
☆
「小説家とは世界中の牡蠣フライについて、どこまでも詳細に書きつづける人間のことである。自分とは何ぞや? そう思うまもなく(そんなことを考えている暇もなく)、僕らは牡蠣フライやメンチカツや海老コロッケについて文章を書き続ける。そしてそれらの事象・事物と自分自身とのあいだに存在する距離や方向を、データとして積み重ねていく。多くを観察し、わずかしか判断を下さない。それが僕の言う『仮説』のおおよその意味だ。そしてそれらの仮説が―積み重ねられた猫たちが―発熱して、そうすることで物語というヴィークル(乗り物)が自然に動き始めるわけだ」
そのように村上春樹は書いています。
ここにある「仮説」と「猫」については、「自己とは何か(あるいはおいしい牡蠣フライの食べ方)」の冒頭近くにこんなことが、記されています。
「良き物語を作るために小説家がなすべきことは、ごく簡単に言ってしまえば、結論を用意することではなく、仮説をただ丹念に積み重ねていくことだ。我々はそれらの仮説を、まるで眠っている猫を手にとるときのように、そっと持ち上げて運び(僕は『仮説』という言葉を使うたびに、いつもぐっすり眠り込んでいる猫たちの姿を思い浮かべる。温かく柔らかく湿った、意識のない猫)、物語というささやかな広場の真ん中に、ひとつまたひとつと積み上げていく。どれくらい有効に正しく猫=仮説を選びとり、どれくらい自然に巧みにそれを積み上げていけるか、それが小説家の力量になる」
このような言葉と、対応した「仮説」と「猫」です。
「ぐっすり眠り込んでいる猫たちの姿を思い浮かべる。温かく柔らかく湿った、意識のない猫」を、そっと持ち上げて運んで、物語というささやかな広場の真ん中に、ひとつひとつ積み上げていくのが小説家であるという言葉は素敵ですね。
☆
さて、ここに一貫して、村上春樹が語っているのは、「本当の自分とは何か?」「自己とは何か」と問うようなことは、小説・物語の道としてはダメであるということではないかと思います。
このような考え方は、もともと村上春樹の中にあったかもしれませんが、私がそのような村上春樹の言葉に初めて接したのは『海辺のカフカ』(2002年)の刊行後に、私と文芸評論家の湯川豊氏と2人で、村上春樹に対して行ったインタビューの時でした。
この「村上春樹を読む」では客観性を担保する意味から、私が村上春樹へインタビューした時に聞いた言葉を記さずに書いていますが、この湯川豊氏とのインタビューは『夢を見るために毎朝僕は目覚めるのです』(2010年)というインタビュー集に収録されていて、既に書籍刊行されていますので、その部分を紹介してもいいでしょう。
☆
『夢を見るために毎朝僕は目覚めるのです』に収録された「『海辺のカフカ』を中心に」という私たちのインタビューの中で村上春樹はこんなふうに語っていました。
「今、世界の人がどうしてこんなに苦しむかというと、自己表現をしなくてはいけないという強迫観念があるからですよ。だからみんな苦しむんです」と。
加えて、こうも語っていました。
「僕はこういうふうに文章で表現して生きている人間だけど、自己表現なんて簡単にできやしないですよ。それは砂漠で塩水を飲むようなものなんです。飲めば飲むほど喉が渇きます。にもかかわらず、日本というか、世界の近代文明というのは自己表現が人間存在にとって不可欠であるということを押しつけているわけです。教育だってそういうものを前提条件として成り立っていますよね。まず自らを知りなさい。自分のアイデンティティーを確立しなさい。他者との差異を認識しなさいと。これは本当に呪いだと思う。だって自分がここにいる存在意味なんて、ほとんどどこにもないわけだから。タマネギの皮むきと同じことです」
これらの言葉を軟らかく、日常の生活の食べ物を通して語っているのが、村上春樹の「牡蠣フライ理論」なのでしょう。
☆
このインタビューは『海辺のカフカ』をめぐって、雑誌「文學界」の2003年4月号に掲載されたものですが、『海辺のカフカ』についての話でしたので、当然、カフカの文学についても村上春樹は語っていました。
「僕は、カフカの書いていることというのは、悪夢の叙述だと思うんですよ」「彼が小説の中でやったことには、現在の作家が悪夢について叙述するのと違って、ほんとに異様なほどのリアリティーがあって、読んでいて、本当にそのまま悪夢の中に入っていきそうなくらいなんだけれど、彼はその悪夢と自分との精神的な関わり方やら、悪夢の出所について書くよりは、むしろ悪夢そのものについてものすごく細密に語っていくわけですね。そしてそこに立ち上がってくる恐怖の肌触りみたいなものを、僕らはほとんどそのまま、読んで感じることができるわけです」「カフカの小説には、不思議だけれど、自我の存在感みたいなものがあまりないんです。悪夢の中で自我がどうのたうつかということにはそれほど興味を持ってないように見える」
これら、カフカの文学について、語る村上春樹の言葉が「牡蠣フライ理論」について語る村上春樹と重なって感じられてきませんか?
<自分自身について説明することは意味のない>こと。<自分自身について書くのは不可能でも><牡蠣フライについて書くことで、そこにあなたと牡蠣フライとのあいだの相関関係や距離感が、自動的に表現され><すなわち、突き詰めていけば、あなた自身について書くことでもあります>という村上春樹の言葉と響き合って感じられると思います。
☆
それと、もう1つ村上春樹の「牡蠣フライ理論」で、大切なことは、自我の追究や自己表現の文学ではなく、「牡蠣フライ」を介在させることによって可能になるオープンな回路を持った物語の重要性です。別に、介在するものが牡蠣フライでなくて、メンチカツや海老コロッケ、トヨタ・カローラでも青山通りでもレオナルド・ディカプリオでもいいわけですが。
私たちのインタビュー「『海辺のカフカ』を中心に」の中でも大きなテーマとして語られ、「自己とは何か(あるいはおいしい牡蠣フライの食べ方)」でも言及されているのは、オウム真理教などのカルト宗教に引き込まれてしまう人々の姿ですが、そのオウム真理教などのカルト宗教に、村上春樹は「牡蠣フライ理論」の物語で対抗しているのです。
「本当の自分とは何か?」という問いかけが、オウム真理教(あるいはほかのカルト宗教)に多くの若者を引き寄せる要因のひとつになっていったのですが、村上春樹は「自己とは何か(あるいはおいしい牡蠣フライの食べ方)」の中で次のように記しています。
「彼らの多くは、自分というものの『本来的な実体』とは何かという、出口の見えない思考トラックに深くはまりこむことによって、現実世界(仮に<現実A>とする)とのフィジカルな接触を少しずつ失っていった」
人は自分を相対化するためには、いくつかの血肉のある仮説をくぐり抜けていかなくはならないのですが、その出口の見えない思考トラックにはまり込んだ人の前に、たまたま強力な外部者が現れて、その外部者がいくつかの仮説をわかりやすいセットメニューにして彼らに手渡します。そこには必要なものの全てが、こぎれいなパッケージになって揃っています。そうすると混乱した<現実A>の世界を持つ者が、より単純で「クリーン」な別の<現実B>に取り替えられてしまうのです。そこでは相対性は退けられ、絶対性がとってかわるのです。
これが、カルト宗教の物語に巻き込まれていってしまう人たちの姿です。小説はこのようなカルト宗教が持つ閉じられた物語とは違う、開かれた物語を創造しなくてはならないのです。
「麻原彰晃が、組織としてのオウム真理教が、多くの若者に対してなしたのは、彼らの物語の輪を完全に閉じてしまうことだった。厚いドアに鍵をかけ、窓の外に捨ててしまうことだった。『本当の自分とは何か?』という問いかけ自体のもたらす閉鎖性を、一まわり大きい、より強固な閉鎖性に置き換えるだけのことだった」
このように、「自己とは何か(あるいはおいしい牡蠣フライの食べ方)」に記されています。
村上春樹の牡蠣フライは、そんなオウム真理教に対抗する牡蠣フライなのです。
「あなたが牡蠣フライについて書くことで、そこにあなたと牡蠣フライとのあいだの相関関係や距離感が、自動的に表現されることになります。すなわち、突き詰めていけば、あなた自身について書くことでもあります」と村上春樹は書いています。
「本当の自分とは何か?」をそのまま追究するのではなく、牡蠣フライを(あるいはメンチカツや海老コロッケ、トヨタ・カローラ、青山通り、レオナルド・ディカプリオを)介在させて、それを書くことよって、自分を含めた世界の相関関係や距離感が表現され、開かれたオープンな回路を持つ物語が生まれていくのです。
今回の「村上春樹を読む」の冒頭に紹介した、五個の牡蠣フライと八個の牡蠣フライというふたつの選択肢があるレストランは、1つのものに閉ざされていかない、いろいろな選択肢があるものの例として、物語のはじめに記されているのでしょう。
☆
「村上さんは食べ物ではカキフライや鰻がお好きのようですね。この「村上さんのところ」でも、他の著作物でも、何度かカキフライと鰻の記述を見たことがあるように思います」というメールが、『村上さんのところ』にありました。(おもも、女性、37歳、主婦、司法試験浪人生)からのメールです。
確かに、村上春樹は鰻好きでもあるので、鰻の登場する小説を紹介しながら、鰻の持つ意味を少しだけ考えてみましょう。
「ナカタはウナギが好きなのです」
「ウナギはオレも好きだよ。ずっと昔に一回食べたきりで、どんな味だったかよく思いだせないけどな」
「はい。ウナギはとくにいいものです。ほかの食べ物とはちょっと違っております。世の中にはかわりのある食べ物もありますが、ウナギのかわりというのは、ナカタの知りますかぎりどこにもありません」
『海辺のカフカ』の第6章に猫の言葉がわかるナカタさんと、猫のオオツカさんとのウナギをめぐるそんな会話があります。
ナカタさんは東京都中野区野方のアパートの小さな部屋に、東京都のホジョを受けながら暮らしていますが、「ときどき猫探し」を頼まれて、そのお礼をいただくと「たまにはウナギを食べることもできます」。また弟が2人いて、ともに頭がよく、1人はイトウチュウのブチョウ、もう1人はツウサンショウで働いていて、「二人とも大きな家に住んで、ウナギを食べております」とも語っています。
さらにミミという猫と出会い、「鯖はナカタもずいぶん好きです。もちろんウナギも好きですが」とナカタさんが言うと、猫のミミも「わたくしもウナギは好物です。いつもいつも食べられるというものではありませんけれど」と言います。
ナカタさんは「まったくそのとおりです。いつもいつも食べられるというものではありません」と言い、「それから二人はめいめいウナギについて沈思黙考した。二人のあいだに、ウナギについて深く考えるだけの時間が流れた」と書かれています。
このウナギをめぐるナカタさんと猫のミミ、オオツカさんとの会話の意味は何でしょうか?
☆
アメリカ文学者の柴田元幸さんが村上春樹らにインタビューした『ナイン・インタビューズ 柴田元幸と9人の作家たち』(2004年)の中で、村上春樹が「小説というのは三者協議じゃなくちゃいけない」という考えを述べています。さらに「三者協議。僕は『うなぎ説』というのを持っているんです」と語っています。
つまり「僕という書き手がいて、読者がいますね。でもその二人でだけじゃ、小説というのは成立しないんですよ。そこにうなぎが必要なんですよ。うなぎなるもの」と語っています。「僕とうなぎと読者で、三人で膝をつき合わせて、いろいろと話し合うわけですよ。そうすると、小説というものがうまく立ち上がってくるんです」と述べているのです。
3人いると、2人でわからなければ「じゃあ、ちょっとうなぎに訊いてみようか」ということになります。するとうなぎが答えてくれますが、おかげで謎が深まったりするというのです。
そのような第三者として設定されたうなぎ。「それは共有されたオルターエゴのようなものかもしれない」と村上春樹は語っています。オルターエゴには、第2の自我、別な自己、分身のような意味があります。
ここにも、閉鎖された、閉じられた物語ではなく、開かれたオープンな物語というものの大切さを語る村上春樹がいると思います。
☆
もちろん、単純にオープンにすればいいというものではありません。
物語は「自我レベル、地上意識レベルでのボイスの呼応というのはだいたいにおいて浅いものです。でも一旦地下に潜って、また出てきたものっていうのは、一見同じように見えても、倍音の深さが違うんです」と村上春樹は川上未映子さんのインタビュー本『みみずくは黄昏に飛びたつ 川上未映子訊く/村上春樹語る』(2017年)の中で語っています。
「一回無意識の層をくぐらせて出てきたマテリアルは、前とは違うものになっている。それに比べて、くぐらせないで、そのまま文章にしたものは響きが浅いわけ。だから僕が物語、物語と言っているのは、要するにマテリアルをくぐらせる作業なんです。それが深くくぐらせばくぐらせるほど、出てくるものが変わってくるんですよね」
さらに。「牡蠣フライを油にくぐらせるみたいに」「表が四十五秒、ひっくり返して十五秒」と、村上春樹は語っています。(共同通信編集委員 小山鉄郎)
******************************************************************************
「村上春樹を読む」が『村上春樹クロニクル』と名前を変えて、春陽堂書店から刊行されます。詳しくはこちらから↓

